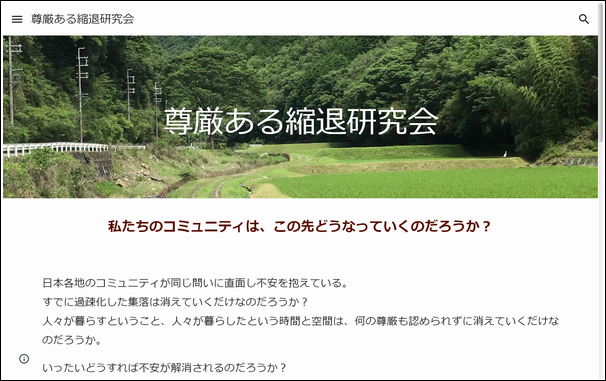尊厳を失わない災害復興へ -「尊厳ある縮退」を見据えたコミュニティの再生・創生-【2021年度学会大会 分科会3 概要報告】
渥美公秀(大阪大学大学院 人間科学研究科)
当分科会では、「尊厳ある縮退」研究会(日本学術振興会 課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業実社会対応プログラム「尊厳ある縮退によるコミュニティの再生と創生」)が行ってきた理論的研究と実践をもとに、右肩下がりの時代における、被災者の尊厳を失わない災害復興について検討した。
登壇者は、当研究会の理論グループ・実践グループ・政策グループから、研究者だけでなく自治体職員やNPO職員などを含めた計9名である。理論グループからはパラダイムロストとしての復興における被災者の主体性の危機が指摘され、被災地発のミュニシパリズムの提案がなされた。また実践グループからは兵庫県上郡町赤松地区でのヒアリング調査、奈良県十津川村の「高森のいえ」プロジェクトの実践などが紹介され、現場の目線として東日本大震災被災者の故郷への想いが紹介された。そして政策グループは、高知県黒潮町での疑似被災や四万十市興津地区のミュージアムを例に、「シュリンキング」としての縮退の過程を豊かにすることの必要性を訴えた。「シュリンク(人口減)=悪」という考え方を廃し、スムーズな移転支援、適切な維持管理によってシュリンキングの質を高めていくべきと主張した。
分科会の議論では、コメンテーターの清水展先生、稲垣文彦先生、澤田雅浩先生からそれぞれコメントをいただいた。清水先生からは、「尊厳ある縮退」という考え方を表すキーワードの重要性をご指摘いただき、「シュリンク」という言葉の使い方について再考した。また二地域居住の考え方は、一所定住、一職専従を当たり前として無理やり成長を続けてきた近代日本全体をも範疇に入れ、日本の新しい在り方を検討するために非常に重要な観点であるとの指摘もあった。
稲垣先生からは、中越地震の復興を例に挙げてコメントがあった。木沢集落では、震災後状況が大きく変化する中、外部支援者の存在によって集落に新たな価値を見出すことができた。パラダイムシフトという混沌の中から秩序が生まれた例である。そして二地域居住については、農機小屋を集落に残し、通い続ける山古志の人々も該当するとしながらも、これは集落を閉じるプロセスの一部でもあると指摘があった。国や自治体も、計画を立て、予算を出している。職員の苦労もあるが、これを積み重ねることが肝要とした。
澤田先生からは、地域から出ていく人々だけでなく、残る世代にも着目すべき-地域の定住人口の増減ではなく、団塊の世代と、その下の世代のニーズを正確に把握すべき-との指摘があった。そのほか、中越地震の「帰ろう山古志」キャンペーンや、人口の自然減/社会減/災害減にも話が及んだ。
今後とも、尊厳を失わない災害復興に向け検討を重ねていきたい。